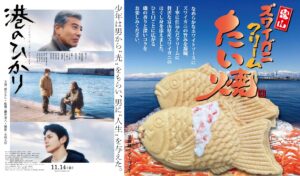日本列島のほぼ真ん中辺りに位置する東海地方は、古くからモノやヒトの往来が盛んで、豊かな自然と過ごしやすい気候に恵まれていることもあり、野菜づくりが盛んな地でした。
そんな東海地方には、数々の伝統野菜が地産地消されており、野菜本来の「旬」や食文化を教えてくれる貴重な存在として親しまれています。

(中津川市内の産直店で購入、「飛騨・美濃伝統野菜 西方いも」のシールが貼ってありました)
旧加子母(かしも)村小郷(おご)地区(現・岐阜県中津川市)で
大切に作り続けられてきたサトイモ

秋から冬にかけて、夏に地中で養分をため込んだ根菜類が旬を迎えます。
中でも、煮物などで主役級の存在感を放つサトイモは、ホクホクしているのに粘りのある食感とほのかな甘みで、口中に幸せをもたらしてくれます。
稲作が始まる前の縄文時代に日本に渡来し、縄文時代には主食だったという説もあるほど、私たち日本人には馴染みのある野菜で、各地で伝統的に作られてきました。
中津川市は岐阜県の東南端に位置しており、その最北端を占めるのが加子母地区。
さらに加子母地区内の最北端に位置するのが、西方いもの主生産地である小郷地区で、海抜約720メートル、北は下呂市、東は長野県王滝村に接する山間の集落です。
この地区は昔、「東方」と「西方」に分かれていて、「西方」に嫁いだ女性たちによって代々作り続けられてきたサトイモが「西方いも」の由来だと伝えられています。
「飛騨・美濃伝統野菜」にも選定されている「西方いも」は、粘り気があって舌触りがきめ細かく、煮崩れしにくく、日もちが良いのが特徴とされます。
気候によって多少変動があるようですが、大体10月から12月が旬だそうです。
旬の期間中は、中津川市内の産直店(道の駅など)などで購入できます(確実に購入するには、事前に産直店に電話で確認することをお薦めします)。
粘りがあるのに、上品なきめ細かさが魅力
イモ類の中で最も低カロリーとされるサトイモ。
豊富な食物繊維のほか、ビタミンB6や、カリウム、マグネシウム、亜鉛、銅といった多彩なミネラル類を含みます。
ぬめりの成分はグルコマンナン(水溶性食物繊維)やガラクタン(多糖類)などで、腸内環境を改善させたり、血中コレステロールを抑える働きがあるとされており、健康機能面でも、ぜひ取り入れたい野菜です。
地元でもよく食べられているそうで、産直店の販売員の女性に聞いた食べ方やインターネットで紹介されている食べ方などを参考に、「西方いも」を使って調理してみましたので、以下にご紹介します。
【ぬめり取り】
※皮をむいたサトイモに塩をもみ込んで水洗いすると、ぬめりが取れて調理しやすくなりますが、栄養素は若干減ります。味に違いは出ないようですので、自己判断でお願いします。
※以下に紹介しているメニューは、ぬめりを取らずに調理しています。

まずは、農林水産省の「うちの郷土料理-次世代に伝えたい大切な味」でも紹介されている「いももち」です。
1)コメと同重量の「西方いも」(皮をむいた状態)を用意して洗っておきます(コメ1合なら「西方いも」は150グラム=大きさによりますが3個ぐらい)。
2)炊飯釜にコメと一口大に切った「西方いも」を入れて、※多めの水と、ひとつまみの塩を入れて炊飯します。
※水分量は、全体が水に浸かるぐらい(感覚的でいいようです)。
3)炊き上がったら全体を※よく混ぜます。
※すりこぎで突いて半殺しにしても、しゃもじで押し付けながら混ぜても、どちらでもいいようです。
4)よく濡らした手に、おにぎりサイズのご飯を取って平たい丸状に成形します。
5)ショウガじょう油や、みたらし風のタレ(さとうとしょう油とみりんを混ぜ合わせてレンジで加熱)に付けて食べます。
新米と旬の「西方いも」を使った作りたての「いももち」は、「秋の実り」を実感できて、格別の味わいです。
どちらの味付けも美味しいですが、辛党の人にはショウガじょう油が、甘党にはみたらし風のタレがお薦めです。

上の「いももち」をすぐに食べない場合は、冷蔵や冷凍したものを、油をしいたフライパンやグリルで焼いて、甘味噌とカラシを付けて食べると、香ばしさとコクが加わって、一味違った美味しさになります。

次は「若い人もよく食べてくれるよ」と教えてもらった、フライド「西方いも」です。
1)皮をむいた「西方いも」を4〜5ミリ角ぐらいの棒状に切って、ポリ袋に入れて小麦粉をまぶします。
2)フライパンに深さ1センチぐらいになるまで油を入れて、弱めの中火で※揚げ焼きします。
※小麦粉で油が汚れるので、1〜2回使用済みで、次はもう捨ててもいいかなという油を使うといいですよ。
3)油から引き上げたら、キッチンペーパーで油切りをし、塩コショウを振りかけます。
サトイモのフライドポテト(?)は初めて食べましたが、ジャガイモで作ったものよりあっさりしていて、とても食べやすかったです。
どんどん手が伸びて、あっという間に食べ終わってしまいました。

フライド「西方いも」は、カレー塩やケチャップといった味変もお薦めだそうで、今回は「さとうじょう油」+「塩コショウ」を試してみました。
揚げたてのフライド「西方いも」を、さとうとしょう油、塩コショウを合わせたボウルに投入し、ザッザッと混ぜるだけです(調味料の分量はお好みで)。
これが思った以上に美味しくて、お酒のおつまみに最高でした。

ご飯が進むおかずとして、「西方いも」のベーコン巻きも作ってみました。
1)皮をむいて縦4つに切った「西方いも」をレンジで加熱します。
2)粗熱がとれた「西方いも」に片栗粉をまぶして、ベーコンで巻きます。
3)ベーコンの表面にも片栗粉をまぶして、油を多めにしいたフライパンで焼きます。
4)全側面に焼き色がついたら、みりんと麺つゆを投入し、煮絡めます。
ベーコンの表面に片栗粉をまぶしているので、甘辛のタレにとろみがついて、より食べやすく、ご飯によく合います。
ベーコンの代わりに、豚や牛の薄切り肉でも美味しそうです。

最後に、定番の「根菜の焚き合わせ」です。
1)食べやすい大きさに切った根菜類と戻した干しシイタケを、お好みのだし汁(いりこ、かつお、こんぶなど)とシイタケの戻し汁で1時間ぐらい煮ます。
2)酒、みりん、しょう油で味を付けてさらに30分ぐらい煮込みます。
※一度冷まして、食べる直前に再度温めると、しっかりと味を染み込むので、お薦めです。
※今回組み合わせた具材は、「西方いも」に、ニンジン、ダイコン、ゴボウ、レンコン、シイタケ、チクワです。
旬の食材が多い上に、栄養豊富で、飽きのこない味なので、常備菜としてたくさん作り置きしておくと助かる一品です。
サトイモはその食味だけでなく、食物繊維や多彩なミネラルが含まれ、食べるときの満足感が大きいのに低カロリーと、健康や美容を気にかけている人にもうれしい野菜です。
昔から親しまれ、地域で大切に栽培され続けてきたサトイモ「西方いも」を、多様な調理方法で楽しみながら、秋の恵みと共に堪能しましょう。
※掲載情報は公開日時点のものとなります