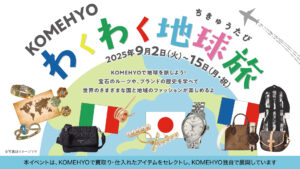かつて、市街地の急速な発展によって「白い街」とも呼ばれた名古屋ですが、道路整備に合わせて街路樹の植栽に注力し、今では、市域における街路樹密度が全国の大都市でトップクラスにまでなりました。
2021年からは、街路樹の大木化や老朽化といった課題を解決し整備を進める「街路樹再生なごやプラン」も始まり、道路空間と調和した街路樹づくりが進められています。
「名古屋の街路樹」では、名古屋市内の、街路樹と街並みが調和した特徴的な風景を取り上げ、その魅力をご紹介していきます。

更新されたばかりの「常緑ヤマボウシの街路樹」
「街路樹再生プラン」を推進中の名古屋では、課題の多い樹種を、事故リスクの少ない樹種に植え替える「更新」を各所で実施しています。
今回は、2025年3月に更新されたばかりの「常緑ヤマボウシの街路樹」をご紹介します。
場所は、金山総合駅の南西すぐの県道115号線の「金山新橋南」交差点~「尾頭橋東」交差点の約250メートルで、(北側の)中区と(南側の)熱田区、(西側の)中川区の境界に当たります。
以前は、成長が早く倒木の事故事例が多い「アオギリ」が植えられていたところですが、2025年3月に、比較的成長速度が遅い「常緑ヤマボウシ」に植え替えられました。
※本記事中の写真は全て2025年6月17日に撮影したものです。

南北を走る国道19号の東側から西の方角を望むと、道沿いに、白い花をたくさん付けた細長い木が立ち並んでいるのが目に入ります。
ここは、江戸時代に東海道の脇往還(わきおうかん)として多くの人々が通った「佐屋街道」の入り口に当たります。
写真左端には江戸時代の標石(しるべいし)も見えるのですが、わかりますか。

この標石は、北面に「北 文政辛巳六月佐屋旅籠屋中」、東面に「東 右 なこや 木曽街道」、西面に「西 右 宮海道 左 なこや道」、南面に「南 左 さや海道 津しま道」と刻まれています。
※文政辛巳は西暦1821年
江戸時代末期に出版された地誌『尾張名所図会』前編巻4にも「佐屋街道標石」という項目があり、西は佐屋海(街)道、北を名古屋、南を熱田とし、ここは三所の堺(境界)というべき所だという記述があります。
街なかで、思わぬ江戸時代との接点を見つけて、不思議な気持ちを味わえるスポットです。

常緑ヤマボウシは両側の歩道沿いに植えられており、植え替えられて間がないからか、どれもほっそりとしています。
木いっぱいに白い花が咲いていて、季節外れのクリスマスツリーのようにも見えますね。

背後には尾頭橋、前方には金山駅があります。

寛永11年(1634年)に架けられた尾頭橋は「堀川七橋」の1つで、江戸時代は佐屋街道を行き交う旅人たちでにぎわったようです。
佐屋街道の整備に合わせて架けられた新しい橋という意味で「新橋」とも呼ばれ、先述のバス停「新橋通」にその名を残しているのだそうです。
現在は平成6年(1994年)に竣工された鋼製桁橋になっており、北の方角にはJRと名鉄が通っているため、赤やシルバーの電車が通る様子を見ることもできます。
比叡山の僧兵になぞらえられた白い花

ヤマボウシは、北海道を除く日本や朝鮮半島、中国に分布するミズキ科の落葉高木です。
ここに植えられているのは「常緑ヤマボウシ」という園芸交配種(常緑のホンコンエンシス、またはその交配種)で、冬も葉が落ちにくい(全く落ちないわけではない)とされています。
そのほかの特徴は普通のヤマボウシに準じているようです(樹形は乱れにくく、花びらに見える先端の尖った白い総苞片が4枚、中央に小さな頭状花序が咲く)。

木の根元に立って見上げるとこんな感じ。
爽やかな葉の緑と花の白が、青空とよく合います。

「ヤマボウシ」は、漢字で書くと「山法師」。
中央の頭状花序が坊主頭に、白い総苞片が肩を覆う頭巾のように見えることから、「山法師」と呼ばれていた比叡山延暦寺の僧兵になぞらえて名付けられたと伝えられています。

総苞片を含めた一つひとつの花は結構小さくて、個体差はありますが、大体直径5センチぐらいです。

中央の頭状花序は真ん中に20~40個ほど集まっているそうですが、それらが咲いているかどうかは、近づいてよく見てみないとわかりません。
開花中の花は、黄緑色の花びらが4枚、めしべが1本、細長いおしべが4本あります。
上の写真では、開花中の頭状花序の右下辺りにアリさんがいますね。
私たち人間から見たら一つひとつが爪の先ほどもないような小さな花でも、アリから見たら自分の頭より大きいんだなあと、改めて認識させられました。

よく見ると、左の花の頭状花序は開花中ですが、右の花の頭状花序は花びらもおしべも全て抜け落ちてしまって、受粉して成長しためしべだけが残っている様子がわかります。
総苞片が付いている(遠目に花が咲いているように見える)状態でも、頭状花序は咲き終わっていることがあったり、まれですが、総苞片が落ちてしまっていても頭状花序が咲いている状態のものがあったりして、面白いです。
総苞片も頭状花序も散ってしまった後の「丸坊主」状態のものも、ツンツンとしていて可愛らしく感じます。
名古屋の街路樹の更新では、事故リスクの高い樹種から、ヤマボウシや、花姿がヤマボウシによく似たハナミズキに植え替えられるところが増えています。
※ハナミズキは、ヤマボウシと同じミズキ科の落葉樹ですが、開花期が5月(ヤマボウシより約1カ月早衣)で、総苞片の先端がへこんでいる(ヤマボウシは尖っている)、実に毒がある(ヤマボウシは食用可)という違いがあリます。
梅雨の時期に咲く花としてはアジサイが有名ですが、梅雨の晴れ間には、爽やかな白い花をたくさん咲かせ、街路樹として目に潤いを与えてくれる常緑ヤマボウシも思い出してもらえたらと思います。
※掲載情報は公開日時点のものとなります