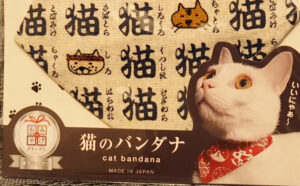いたずらばかりしている子狐が村人に罪滅ぼしをしていたところ、そうとは知らずに火縄銃で撃たれてしまう。短く平易だが深い余韻のある新美南吉の童話「ごんぎつね」は、小学校4年生向け国語教科書の定番だ。1956(昭和31)にはじめて採用されたのを機にどの教科書にも載り、日本人の多くが一度は読む作品となる。低学年から高学年へ成長する過程にふさわしい内容を備える点が、選ばれつづける理由だろう。
「小学生のとき、授業でこの作品を知り、夏休みに図書館へ通って作者が書いたほかの作品を読みふけりました。そして、30代半ば、詩の編集者として南吉の詩を再発見したのです」
と『人間に生れてしまったけれど 新美南吉の詩を歩く』(かもがわ出版)をまとめたPippoさんは言う。書名は南吉の詩のなかでとくに惹かれた、「墓碑銘」という作品の一節からつけられた。思春期から人間として生きる難しさを感じてきたPippoさんに、響くものがあったのである。
けれど何かの間違いで
彼は人間の世界に
生れてしまった
彼には人間達のように
お互を傷つけあって生きる勇気は
とてもなかった
(「墓碑銘」、新美南吉)

新美南吉は1913(大正2)年、愛知県半田市(当時は半田町)に生まれ育ち、半田や河和の小学校、安城の女子高校で教師として働く傍ら、鈴木三重吉の主宰する児童雑誌『赤い鳥』などに作品を発表した。その生きざまは決して平坦でなかったことを、編集者として『田村隆一全詩集』(思潮社)などに携わったのち、“近代詩伝道師”の肩書きで活動するPippoさんは現地を訪ね、解き明かしていく。
「兄が名古屋に本社のある飲料メーカーに就職したことから行ったことがあったくらいでしたが、私が主宰している詩の読書会を通じて親しくなった友人夫妻が名古屋で暮らすようになり、南吉の故郷を訪ねてみようということになりました。2021年のことです。行ってみたら童話や詩そのものの世界がいまも残っていることに驚かされました」
以来、Pippoさんは2年をかけ、5回にわたり半田周辺を取材して回る。最初はZINE(ジン)と呼ばれる小冊子にでもまとめようかと考えていたが、本にしないかと編集者に声をかけられて実現した。

本書がユニークなのは、まず実際に自分の目で見た現地の様子をもとに生涯を追い、そのうえで南吉の詩と童話をセレクトして掲載し、さらにPippoさんが中心となっている読書会に参加した人びとの感想をまとめた三部構成になっている点だ。
昭和の初期、『赤い鳥』周辺で活躍しながらも結核で若くして亡くなったという漠然とした生涯が、就職も恋愛もうまくいかず、才能に恵まれながら作家としての活動は困難を極めた実像が浮かび上がってくる。
本書には南吉の生家や、「ごんぎつね」の舞台となった山や川の写真などが多数、掲載されている。昭和の時代にたくさんつくられた文学全集には、たいてい巻頭に作家の写真アルバムが数ページにわたって掲載されていたのに通じる。家族写真や初版本の表紙、自筆原稿用紙の複写などから構成されているのだが、名作の作者がより身近に感じられ、作品理解につながった。
「作品が生まれた風景を見ることで、よりリアルに、立体的に浮かび上がってきました。“文学散歩”がよりおもしろくなって、いまは立原道造や平井晩村を追ったりしています」

文学作品を現地で読み解くルポルタージュになっているのだが、潜行するものを捕らえようとする独自の目線を行間に感じた。詩書出版という、編集者のなかでも特異な経歴が背景にありそうだが、意外な答えが返ってきた。
「いつも釣り道具を車に積んでいて、文学散歩をしながら、ポイントを見つけるたび、すかさず竿を出しています。父が釣りを趣味としていて、幼いころから連れていかれたのがはじまりです」
常滑のあたりにハゼの好ポイントがあり、とくに秋にはたくさん釣れるのだそうだ。最近の釣りブームでは珍しくなくなったが、女性一人でも躊躇はないという。
“近代詩伝道師”としてPippoさんは、神保町(東京)の喫茶店とリモートでの開催をベースに、全国各地の文学館・書店などでも詩の読書会をおこなっている。
「参加者は女性が多めですが、男女ともに一人で来られる方が大半で、ご夫妻で参加してくださる方もいらっしゃいます」
昭和の時代、全国各地に詩の同人組織があり、読む人も書く者もたくさんいた。いまはそのころのような大所帯の組織は数少なくなったが、ZINEやインターネットで思い思いに詩を発表する人が増えている。