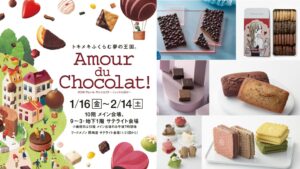静岡県の西端、湖西市の新居宿。旧東海道のほぼ真ん中あたりにある。真ん中あたりだから検問にはちょうどいい。ここには検問所の役割を果たした関所の姿が残されている。当時の姿がそのまま残されているのは全国でもここだけらしい。

東海道を旅する人たち、参勤交代をする人たち、わるだくみをしようとする人たち。入り鉄砲に出女は特に厳しく取り締まられた。そんな全ての人たちがここを通り過ぎようとし、無事通れた人もいれば、通り過ぎることができなかった人たちもいる。関所の建物を眺めながら、それらの人たちの姿を想像する。おそらく当時のまま植わっている松の木や、再現された船着き場が臨場感を増してくれる。


本物の姿形が残された新居関所を覗いてみる。建物はシンプルでまさに検問の機能のみを重視した造り。そこに等身大の検問者たちの姿。小学校の修学旅行、二条城で大政奉還を再現した人形にぞっとしたことを思い出す。


関所を出るとすぐそこには旅籠紀伊国屋。宿場町だから当然、宿が何軒か軒を連ねていた。今は、当時の姿を忠実に再現した資料館となっている。資料館といっても、展示解説があるタイプの資料館ではない。当時の客室や庭や台所などの姿を見せることが貴重な資料だ。



街道から少し裏手に行くとかつての芸者置屋兼小料理屋がある。今は、小松楼まちづくり交流館として市民ギャラリーも兼ねた社交場になっているが、2階に上がると、当時の芸者さんが使っていた三味線や鏡などがあり、歴史と文化を伝える。2階の軒先も雰囲気が残され、ここから道行く人たちに声をかけていた芸者さんたちの姿が目に浮かぶ。



かつての街道筋は、地域の幹線道路になっていて車の通行量は多い。いわゆる古い町並みの情緒が残っているわけではないが、ここ各所に歴史を表す石碑などが建っている。

かつての宿場町を彷彿させてくれるのが、酒屋やまんじゅう屋やせんべい屋さん。調べてはいないが、代々伝わってきた老舗なのだろう。看板や建物、店のネーミングにその歴史を感じる。



新居が面白いのは、これらに違和感なく混ざっている飲食店たち。古民家レストランやカフェ、古書店など、最近この町に誕生した新しい顔たちだ。伝えられてきた本物の歴史文化
とこれからこの町の文化を作っていくだろう店舗たち。この町はこの対比が面白い。