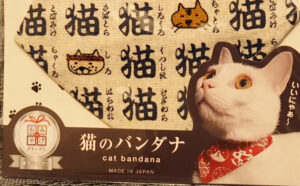想定外にいい空間といい時間を過ごした諸戸氏庭園と六華苑を後に、この日の本来の目的だった旧東海道桑名宿へ。六華苑からは海辺の道を歩いてすぐ。いや、目の前に広がる広大な水面を海だと思っていたが、ここは海なのか川なのか。ここは、旧東海道において唯一海路で結ばれた「七里の渡し」の船着き場。だから、てっきり海と思っていたが、どうやら川だ。江戸時代は海だったかも知れないが、いずれにしても海から近くに位置するところに桑名宿はある。

スタート地点には、大きな鳥居が待ち構える。鳥居があるのにその向こうに神社がない。江戸時代の旅人は、ここまで舟で渡り、そこから二手に分かれたという。西へと東海道の旅を続ける人、そして南へ伊勢神宮に向かう伊勢道の旅を続ける人。この鳥居は伊勢国一の鳥居であり、神宮式年遷宮で取り換えられた内宮の宇治橋の鳥居がこちらに移設されるという。その伊勢神宮への道の入口として、船着き場のすぐそばに鳥居が立っている。一生に一度はお伊勢参りと言われた時代。伊勢神宮へ行きたいが、京へ向かわなければならない東海道組の人たちはここでお伊勢さんに向けてお参りをしたという。


船着き場のそばには桑名城の櫓を再現した施設が建つ。鳥居の裏の階段を降りると、そこからは旧東海道。ほぼ現代の住宅街となっており、当時の面影を残すような旧街道の雰囲気はない。唯一、一軒だけ建っていた旅籠らしき建物の前を通り、旧東海道をゆく。



しばらく歩くと青銅でできた春日神社の大鳥居。江戸時代から350年間立ち続けるひとつの桑名の歴史的シンボル。近くには、1704年創業と300年の歴史を持つ饅頭屋。江戸時代から旅をする人たちの多くがここで休憩し、寛いだであろう。


さらに歩くと、堀川と石垣が見えてきた。海の名城と言われた桑名城。城の建物は残されていないが、これらの石垣が歴史の証人として存在する。



桑名城の城跡へ。今は、九華公園として市民に親しまれる。満開のつつじが咲くなか、ゆったりとした空間のかつての本丸、二の丸の庭園を歩いた。


桑名の歴史文化まちめぐり。思っていた以上に充実していて、気づけば4時間ほど歩いていた。庭園や公園の季節感もあり、また違う季節に歩きたい。