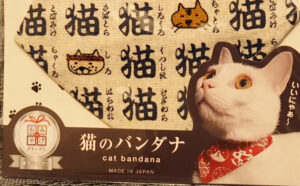東海地方には、文化や歴史、自然の息吹や時の流れを感じることができる場所が数多く存在します。そんな、ひととき日常から離れて「ほっ」とできるスポットを紹介していきます。
今回は、国指定の史跡「青塚古墳」を中心に形成された「青塚古墳史跡公園」(愛知県犬山市)を取り上げます。

(名古屋大学考古学研究室提供/2023年6月撮影)
※東側から西方向を見たところ(写真の手前側にガイダンス施設「まほらの館」がありますが、この写真には入っていません)
県内で2番目の大きさを誇る前方後円墳
愛知県の最北端に位置し、木曽川によって運ばれた砂等が堆積した扇状地が広がる犬山市では、旧石器時代から古人の生活の跡が数多く見つかっており、2023年時点で62件の古墳が確認されています。
中でも、市の南西部に鎮座する前方後円墳「青塚古墳」は、墳長約123メートル、前方部の最長部分の幅が62メートル、後円部の直径が約78メートルと市内最大で、県内でも2番目の大きさを誇ります。
※県内最大サイズの古墳は名古屋市熱田区の断夫山古墳(墳長約151メートル)。
当地は犬山扇状地に発達した下位段丘堆積層の西端部に当たるため、西に接する丹羽郡大口町の水田面から約2メートル高くなっており、西側から見ると台地上に大きな前方後円墳を見上げる形となるそうで、その視覚的効果も狙ってこの地に築造されたのではと推測されているそうです。
古墳時代前期にあたる4世紀中ごろの築造と推定され、当古墳に先立って築造されたと伝わる同市内の「東之宮古墳」と共に、国の史跡に指定されています。
後円部の高さは約12メートルあり、天正12年(1584)の小牧長久手の戦いの際には、秀吉陣営の砦(青塚砦)として使用されたこともわかっています。
そんな青塚古墳の保存・活用を目的に、2000年に整備されたのが「日本の歴史公園100選」にも選定されている青塚古墳史跡公園(約2.1万平方メートル)です。

※以下、本記事掲載の写真は、全て2025年9月25日撮影
青塚古墳は、当地から3.5キロほど東にある大縣(おおあがた)神社のご祭神の墳墓であると伝わり、社地でもあるため、地域の人々によって大切に守られてきたという経緯があります。
特別な許可がない限り、墳丘への一般の人の立ち入りは禁止されていますが、麓部分までは近づくことができます。

園内南東部には、ガイダンス施設「まほらの館(やかた)」があります。
青塚古墳や市内の遺跡について、パネルや出土品の展示を通してわかりやすく紹介しているので、まずはこちらで古墳のことを学んでから園内を散策すると、より楽しめると思います。

中央部には、青塚古墳から出土した壺型埴輪(つぼがたはにわ)※や、円筒埴輪が配置されています。
壁面には、市内各地の古墳から出土した埴輪や石鏃(せきぞく=石でできたヤジリ)、鉄鏃、勾玉(まがたま)などのほか、様々なテーマで古墳について理解しやすくまとめてあるパネルが展示してあり、思わず見入ってしまいました。
※同館職員のお話によると、底に穴が開けられている壺型埴輪(土器ではない)は、古墳時代よりも前の弥生時代ごろから、尾張北部ではお墓に置く習慣があったようです。人型や馬型などの埴輪が出現するのは、青塚古墳築造時より少し新しい古墳時代中期ごろからのようです。

一部※を除き、ほとんどの展示品は実際に出土した現物が展示してあるため、1600~1700年ほど前の先人の手によってつくり出された副葬品等を間近に見られる貴重な場所です。
※東之宮古墳からの出土品である銅鏡等(国重文)は京都国立博物館で保管・展示されているため、「まほらの館」内ではレプリカが展示されています。

近隣に分布する古墳たちが、その形や規模がわかるように展示してあり、とてもわかりやすいです。

館内には、展示室のほか、室内から古墳を眺められるレストスペースや研修室もあり、古墳グッズの物販コーナーもあります。
「古墳グッズって何?」と思って見てみると、青塚古墳や東之宮古墳をかたどった消しゴムやキーホルダー、マグネット、ペーパークラフトのほか、最近古墳ファンに認知されつつある「御墳印(ごふんいん)」や、オリジナルの火打金もあり、結構面白いです。
消しゴムやキーホルダーがその場で自作することもできて、完成品より安価に入手できるという事実には驚かされました(消しゴムの完成品は200円/自作は100円、キーホルダーの完成品は300円/自作は200円)!

研修室は通常、講習会などに使われるそうですが、空いているときは自由に休憩に使ったりできるそうで、大きな窓から落ち着いて青塚古墳を眺めることができます。
目の前に広がる前方後円墳の迫力
まほらの館で古墳についての知識を仕入れたら、古墳周辺の散策へ出かけてみましょう。

まほらの館のすぐ前から見ると、真横から古墳の形を確認することができます。
向かって左が前方部(高さ約7メートル)で、右側が後円部(同約12メートル)です。
上の写真では、公園の向こう側の建物が重なって見えてしまっているため、前方部と後円部の高さはあまり差がないように見えますが、実際は高さが結構違っていて、前方部は二段丘、後円部は三段丘になっているのがわかります。

手前が前方部、向こう側が後円部です。

青塚古墳の西側には、南北に細長い小さな池があるのですが、その南側から墳丘を見たところです。
池にはガマが茂り、ほとりにヒガンバナが咲いていました。
墳丘の一段目にぐるりと巡らされた赤い壺型埴輪と相まって、絵になる風景です。
調査によると、古墳築造時は墳丘の各段にベンガラ(赤い顔料)で塗られた壺型埴輪を2メートル間隔で置いていたようです。
公園として整備する際、当時の雰囲気を演出するために、最下層の一段目にだけ赤い壺型埴輪(レプリカ)を設置し、墳丘のふちに水はけのための溝を施して石を敷いたそうで、この石敷きの溝の部分までは一般の人も立ち入ることができます。

オミナエシやススキなど、秋の草花と古墳の組み合わせに、郷愁を感じます。

眼前に見えるのは後円部ですが、向こう側にある前方部はほぼ重なってしまっているため、ただの小高い丘のように見えますね。
県営名古屋空港や航空自衛隊小牧基地が近く、上空を飛行機が飛んでいる光景がよく見られます。
古墳と飛行機の組み合わせがなんともシュールで、思わず笑ってしまいました。

公園東部は「ろくごうの森」と名付けられ、木々や多様な草花が植えられた緑地になっています。
公園脇の歩道からは、カラフルな花越しに古墳も華やいで見えるから不思議です。

園内には、のんびり古墳を鑑賞できるよう、まばらにベンチが置かれています。
古墳というと、うっそうとした木々に覆われて、自分の目線からは古墳の形状を実感できないというイメージを持っていましたが、地域の人々によって年数回草刈りが行われているという青塚古墳は、古墳の代表的な形式の前方後円墳のフォルムを360度から眺められる貴重な場所であり、見る場所によって古墳の違う表情を発見できるのが面白いなあと感じました。
大縣神社のご祭神の墳墓と伝えられている当古墳は同神社の社地でもあり、実はまだ本格的な内部調査が行われていないそうです。
歴史的な学術研究のためだとしても、古墳内部の発掘調査はお墓を暴くことになるというジレンマもあるようです。
時代を超えて、外側は地域の人々の手で美観が保たれ、内部は千数百年前の人や副葬品たちの眠りを妨げることなく守られてきた古墳なのだなあと実感しました。
日常を離れ「ホッ」とするために、古代から脈々と受け継がれている人の営みの息吹を感じるために、何度でも訪れたい場所です。
■青塚古墳史跡公園(あおつかこふんしせきこうえん) ※入園自由
〈2000年開園/日本の歴史公園100選〉
・住所:愛知県犬山市字青塚22-3
・TEL:0568-68-2272(まほらの館)
・まほらの館の開館時間:午前9時~午後5時(毎週月曜と年末年始休館)
・駐車場(無料)の利用可能日時は、まほらの館に準じます。
※10月は、青塚古墳にて大縣神社崇敬奉賛会主催の「墓前祭」、NPO法人古代邇波(にわ)の里・文化遺産ネットワーク主催の「青塚古代音楽絵巻」が行われます。
◎「墓前祭」は、毎年中秋の名月に近い週末の夕刻に開催(2025年は10月4日のようです)。
詳細は、大縣神社にご確認ください。
◎「青塚古代音楽絵巻」は2015年から始まり(不開催の年もあり)、
8回目を迎える2025年は、10月19日(日)15時~16時に開催予定。
青塚古墳の麓で、「はにわ娘歌姫隊」によるミニライブと、古代音楽劇集団「夢舞台」らによる野外劇が行われます。
観覧無料。雨天時は「まほらの館」内で実施予定。
詳細は、まほらの館にご確認ください。
※掲載情報は公開日時点のものとなります。